岩村暢子氏の「残念和食にもワケがある」を読みながら、私たちが育ってきた昭和40年代の食文化と現在のそれとの想像を超えるギャップに愕然とし、「食育」と政府を挙げて声高に叫ばれる危機意識がよくわかりました。
いつもながら岩村氏の、膨大なデータを「アナログ」で処理し、そのデータの意味する実態の威力をまざまざと見せつける偉業には感服させられました。
まさに現在の日本の庶民の食卓文化そのものが、掛け値なしに白日のもとにさらされています。
食べることは健康になる目的ではないとは、先日の佐藤達夫氏の言葉ですが、岩村氏が明らかにした平成の食卓では、家族の健康はとうてい維持できないのではないかと危惧しています。
テレビ番組で、カップルの女性にある典型的なメニュー(例えば酢豚など)を挙げて、それを調理してもらう企画があって(テレビがないので知らないのですが、患者さんの談話から)、その際の女性の料理に対する知識がびっくりするほどない理由がよくわかったような気がします。
「食べたら、その料理の素材や作り方は、想像できるだろう。」という思い込みは、岩村氏が紹介している平成の食卓においては不可能なことだとよくわかりました。
いわゆる典型的なメニューさえも、原型をとどめていない。
家族の(作り手である主婦の都合や子供の)趣向を最優先として、食がただ単に好きなものを好きなように食文化や栄養を完全に無視して、食べるという行為だけに特化されたものになっているからだと思います。
食文化というものは、本能に逆らって(断食もあるように)、民族の置かれた環境や信条によって形成され、その規制はタブーとして数々の食事作法として伝承されていきます。そしてそれは個人だけでは継承できません。
昭和の食卓文化もそれが形成された背景には、伝統的な日本食に加えて、経済成長の恩恵を受けた豊かさが食の欧米化を促し、きっと昭和の主婦も明治・大正生まれの姑の白い目にさらされながらも、家族の健康のことを考え、また、その時々のマスコミなどによって生み出される情報に影響されながら、築き上げてきたものだと思います。
その結果が日本人の体格の良さと寿命の長寿化という栄養の成果が表れた形になったのではないかと思います。
日本の食文化(少なくとも昭和の食文化)の崩壊の原因は、個人化が浸透しすぎてしまったことにあるように感じます。個々の欲求や嗜好を抑圧する作用も持つ文化を、もはや形成できなくなってきている実態を、原点である食卓で見せつけられたように感じます。
家庭が文化を伝える教育の場ではなくなっている。ではだれが文化を伝える担い手になるのか。
平成の食卓の有り様から感じました。
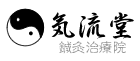
コメントをお書きください